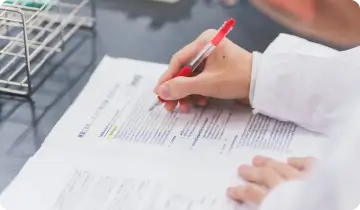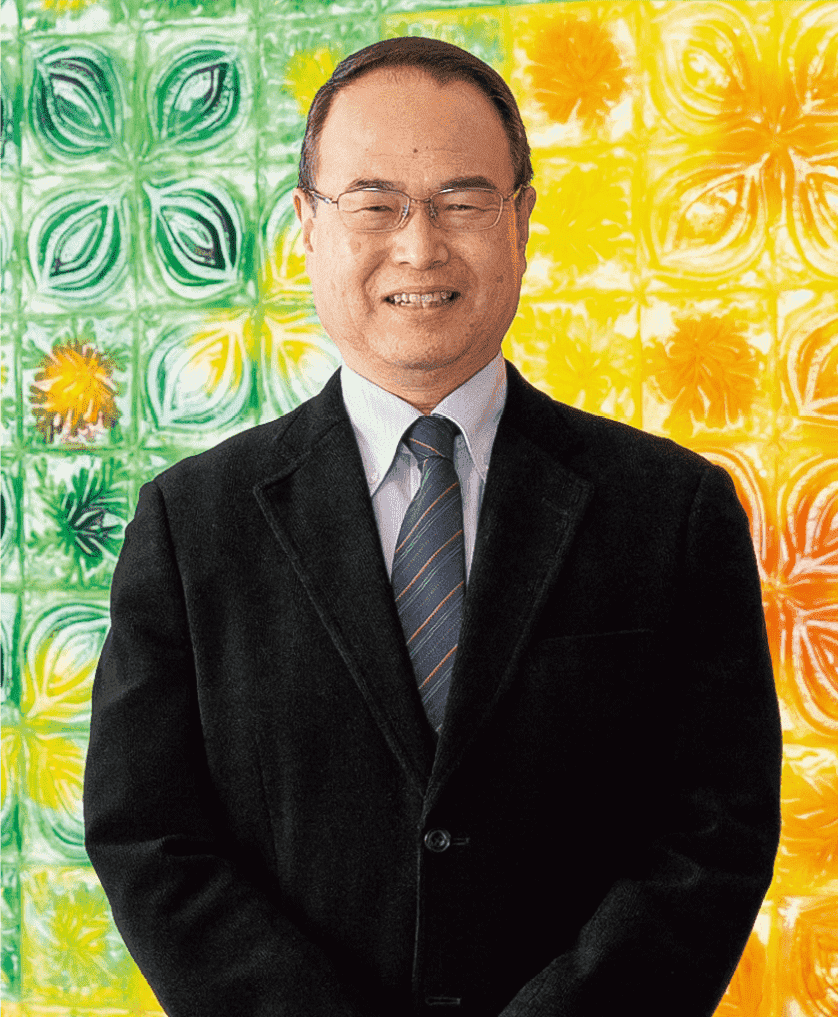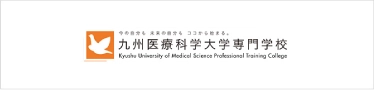[通信制]
社会福祉学研究科 博士
(前期)課程
多岐にわたる社会福祉の実践的研究を行う
社会福祉の「援助技術」といわれるものは、個々の対象者に対するケアワークから、バリアフリーの街づくり、所得保障、支援制度に関する法整備とその制度の充実、地域の社会福祉資源の整備と活用など、ソーシャルワーカーを軸とした幅広い援助活動の方法・技術を含みます。
この幅広い領域を網羅しながら、「実践的研究」を展開していくのが社会福祉学研究科です。多岐にわたる科目の履修・学習を進めながら、年2回のスクーリングで学習の成果を検討・議論し、修士論文の作成を目指します。
MESSAGE
研究科長挨拶
カリキュラム
カリキュラム表
必修科目
選択科目
T=印刷授業科目
TS=印刷授業科目と対面授業の複合科目
必修科目
| 担当教員 | 開講年次 | 単位 | |
|
社会福祉学特論 |
栗栖 照雄 横山 裕 |
1 | 4 |
専門選択科目
| 担当教員 | 開講年次 | 単位 | |
|
社会福祉学特論Ⅰ - 行動療法論 |
前田 直樹 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅰ - 人間動物関係論 |
加藤 謙介 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅱ - アダプテッド・スポーツ論 |
正野 知基 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅲ - 研究法・調査法 |
三宮 基裕 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅳ - 高齢者福祉論 |
清水 径子 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅴ - 東洋介護福祉論 |
渡邊 一平 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅵ - 地域福祉論 |
平川 忠敏 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅶ - 権利擁護論 |
日田 剛 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅷ - 施設経営論 |
鬼﨑 信好 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅸ - 生活支援技術論 |
清水 径子 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅹ - スクールソーシャルワーク論 |
横山 裕 | 1・2 | 4 |
|
社会福祉学特論Ⅺ - コミュニティ・ソーシャルワーク論 |
川﨑 順子 | 1・2 | 4 |
総合科目
| 担当教員 | 開講年次 | 単位 | |
|
特別研究 |
加藤 謙介 川﨑 順子 清水 径子 正野 知基 西田 美香 日田 剛 前田 直樹 松山 光生 横山 裕 渡邊 一平 |
1~2 | 6 |
修了要件
必修2科目10単位、専門選択5科目20単位以上、合計30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格すること。
POLICY
3つのポリシー
POLICY01
ディプロマ・ポリシー
卒業認定・学位授与の方針
九州医療科学大学大学院(通信制)社会福祉学研究科博士(前期)課程(以下、「本研究科」)では、本研究科の課程を修め、30単位の単位修得と学位論文等の条件を満たし、社会福祉における諸問題を解明し、課題にこたえる研究能力、実践力を修得し、福祉分野において指導的立場に立てる人材として、下記の力を身につけた人に対して学位を授与します。
1.高度専門職業人としての高潔な倫理観と問題解決能力
高度専門職業人として高潔な倫理観と問題解決能力を身につけ、実践することができる。
2.社会福祉にかかわる高度な専門的知識・技能の活用力
社会福祉にかかわる高度な専門的知識・技能を幅広く身につけ、活用することができる。
3.論理的に意見を示して実践する能力
主観ではなく客観的な事実に基づき、論理的に意見を示して実践することができる。
4.社会福祉における課題に対する論理的思考力、洞察力
社会福祉における課題に対する論理的思考力、洞察力を有し、課題に対する分析、研究方法を身につけ、実践することができる。
POLICY02
カリキュラム・ポリシー
教育課程編成の方針
本研究科は、建学の理念および修了認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げた目標を達成するために、次のような教育内容と方法を取り入れた授業を実施し、教育評価を行います。
1. 教育内容
1.必修科目および専門選択科目、スクーリング時の指導を通して、高度専門職業人としての実践の場における倫理問題を自己解決できる倫理思考能力、さらに、現場での業務に必要な社会福祉にかかわる多角的な知識を習得することで、福祉現場が直面する課題への対処能力を修得します。
2.必修科目および専門選択科目を通して、社会福祉にかかわる高度な専門的知識・技能を幅広く修得し、さらにレポート課題において、主観ではなく客観的な事実に基づき、論理的に意見を示す能力を修得します。
3.特別研究および修士論文作成を通して、社会福祉における課題に対して論理的に思考し、問題解決に向けての分析や研究方法を身につけ、実践する能力を修得します。
2. 教育方法
1.各科目はシラバス(授業の概要、一般目標、到達目標、授業計画、評価方法などを示したもの)に記載の教育方法に沿って行います。
2.必修科目および専門選択科目の履修期間は1年間で、3回の課題レポート提出により授業科目の理解度を判定し、科目修了試験受験の可否を決定します。
3.大学院生および指導教員全員参加のもと、1年次の夏期スクーリングで「研究テーマ発表」、冬期スクーリングで「研究計画発表」、2年次の夏期スクーリングで「中間発表」を実施し、質疑応答を通して研究の内容や方法について確認・修正を行います。
3. 教育評価
1.冬期スクーリング時に、各科目の修得度を確認するために科目修了試験を実施し、シラバスに記載の評価方法に沿って合否を判定します。
2.修了時には、修士論文の審査および最終試験の合格を求めます。
POLICY03
アドミッション・ポリシー
入学者受入の方針
本研究科では、修了認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)及び教育課程の編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲を備えた人を求めます。
1. 教育内容
1.福祉、医療、保健、教育、看護等にかかわる幅広い分野で活躍しており、多様化、複雑化、深刻化する現代社会に応じた問題解決能力、実践力の修得を目指す意欲を持つ。
2.社会福祉にかかわる基礎的な知識・技能を身につけている。
3.豊かな人間性と社会福祉分野の専門職業人として高い資質を持つ。
TEACHER
教員メッセージ
教授・学科長
前田 直樹
大学院担当教員の前田直樹と申します。専門は行動療法で、不登校を中心とした回避行動の行動論的アプローチを研究しております。心理学や臨床心理学には色々な立場や考え方がありますが、中でも行動療法は様々なデータに基づいた科学的なアプローチです。このアプローチが心理や福祉の現場でこれまで以上に活用されれば、様々な社会的な問題をより効果的に解決することが可能になると思います。
教授
横山 裕
「学びて時に之を習う、また説ばしからずや。朋の遠方より来るあり、また楽しからずや」 これは「学習」という言葉の由来となった『論語』の冒頭の文章で す。通信制で学ぶことは、皆さんにとってよろこばしいことだと思います。またスクーリングで本学につどい学友と顔を合わせ語り合えることは、きっと楽しい ことだと思います。喜びと楽しみを噛み締めながら学んでいきましょう。