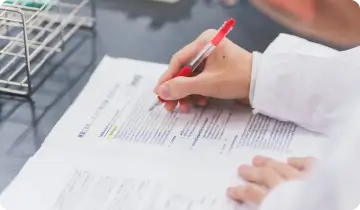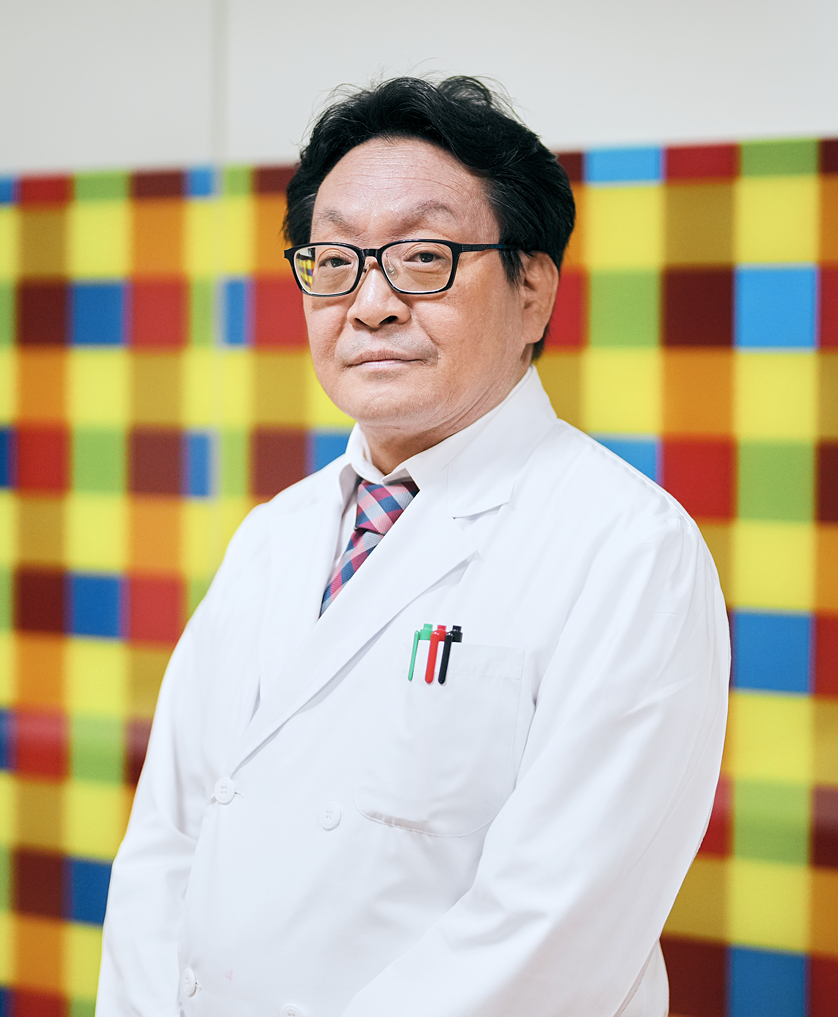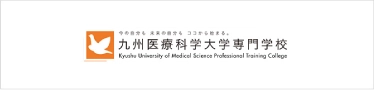SCROLL
- DEPARTMENT OF PHARMACY
- DEPARTMENT OF PHARMACY
- DEPARTMENT OF PHARMACY
- DEPARTMENT OF PHARMACY
- DEPARTMENT OF PHARMACY
- DEPARTMENT OF PHARMACY
資格からコースを選ぶ
カテゴリからコースを選ぶ
Search results
POLICY
3つのポリシー
POLICY01
ディプロマ・ポリシー
卒業認定・学位授与の方針
薬学科(以下、「本学科」)では、本学の課程を修め、所定の単位を満たし、かつ地域医療や社会の期待に応えて、個々の患者や生活者のニーズに対応できる薬剤師となるために必要な下記の資質について、最低限以上の基礎的な力を身につけた者に学位を授与します。
1.薬剤師としての倫理観
医療人として高い倫理観と豊かな人間性を持ち、患者、家族、生活者の人権や尊厳に配慮して、人の命と健康な生活を守るために行動できる。
2.患者を中心としたチーム医療への参画
常に患者の立場に立ち、コミュニケーション能力をもって患者・患者家族・他の医療職種と相互の立場を尊重した人間関係を構築してチーム医療へ参画できる。
3.最適な薬物療法の実践
医薬品・化学物質等の生体及び環境に対する影響を理解した上で、適切に管理・供給し、個々の患者に適した安全で効果的な薬物療法を実践できる。
4.地域の保健医療への貢献
地域住民の視点に立ち、地域の保健医療のニーズを理解した上で、他職種と連携して人々の健康増進と公衆衛生の向上に貢献できる。
5.医療の進歩への貢献
自己研鑽に努め、問題点や社会的動向を把握し、解決に向けて取り組む姿勢を持つとともに、次世代を担う人材の養成を行い、薬学・医療の進歩と改善に貢献できる。
POLICY02
カリキュラム・ポリシー
教育課程編成の方針
本学科では、ディプロマ・ポリシー(DP)に掲げた資質を修得するために必要な科目を大学共通基礎科目、学科基礎科目、学科専門導入科目、学科専門科目の教育を通じて講義、演習、実習、問題解決研究を組み合わせた体系的な授業を行います。
1.教育内容【教育課程編成の考え方】
(1) 薬学教育モデル・コア・カリキュラムの内容を網羅する。
(2) 学科の理念、教育研究上の目的、DPに基づいた大学独自の教育内容を含める。
(3) 薬学臨床教育の実施においては、「薬学実務実習ガイドライン」に準拠する。
(4) 6年間の教育課程を「第1期(1年生~2年生前期) 主体的な学習への転換と医療人としての自覚の涵養」「第2期(2年生後期~4年生後期) 基礎・臨床薬学の学習と知識・技術の統合」「第3期(5~6年生) 薬物治療の実践と課題解決力の涵養」の3段階に分類する。
2.教育方法【教育課程実施の方法】
(1)大学共通基礎科目、学科基礎科目、学科専門導入科目を配置し、特に学科基礎科目および学科専門導入科目においては理解度の向上のため全ての科目で演習を積極的に取り入れる。(第1期)
(2)学科専門科目として講義・演習(PBL)、実習(基礎薬学実習および臨床実践)を豊富に取り込み、パフォーマンス評価(レポート、ポートフォリオ、プレゼンテーション、実験の実施)を積極的に行う。また、DP1~DP4の科目群に対する基礎的な理解度を測定するため、基礎薬学総合演習を配置する(第2期)。
(3)実務実習および特別研究を配置するほか、臨床薬学に関わる演習科目を配置し、パフォーマンス評価(ポートフォリオ、実務実習の概略評価、プレゼンテーション、卒業研究の実施・発表・論文化)を積極的に行う。また、DP1~DP4の科目群に対する総合的な理解度を測定するため、薬学総合演習を配置する(第3期)。
(4) 全ての開講科目について、それぞれの学習目標の到達度を適正に評価するための方法及び基準(テスト、レポート、パフォーマンス評価の基準やウエイト)を定め、これらをシラバスに明記して学生に周知し、学修成果を厳格かつ公正に評価する。
3.教育評価【学修成果の評価方法】
(1) 学科のアセスメント・ポリシーに従って評価を行う。
(2) 第1期~第3期の転換期においては個々の学生の成績表とカリキュラム・マップおよびシラバスに記載されたDPへの寄与率を用いてDPへの達成度を測定する。DP達成度は学科で定めた到達目標と比較することで学生指導および教育課程編成の見直しに活用する。
POLICY03
アドミッション・ポリシー
入学者受入の方針
本学科は、高い倫理観と高度な専門的知識・技能をもった薬剤師を養成することを目的としています。また、旺盛な探求心を有し、協調性と広い視野をもって医療現場や地域の問題を解決できる人材の養成を目標としています。このため、次のような学生を求めています。
1.求める学生像
(1)医療人として、医療現場や地域で活躍するという強い意志・意欲を持った学生
(2)医療・薬学に強い興味を持ち、学習意欲が旺盛な学生
(3)薬学を学ぶために必要な科学的基礎知識と日本語・外国語の基礎学力を備えた学生
(4)ひとに対する深い思いやりと優れたコミュニケーション能力を持った学生
2.入学までに修得すべき学力・能力
専門的な知識・技能を学習するための基盤となる以下の学力・能力。特に、医薬品の構造や人体への影響、生命現象のしくみを理解するための基礎となる化学の知識は重要です。
(1)「国語」:文章読解力、コミュニケーション力、表現力。
(2)「数学」:数学的思考力、表現力、基礎的な計算力。
(3)「理科」:自然科学の総合的理解力、論理的思考力。
(4)「英語」:読解力、コミュニケーション力、表現力。
(5)「その他」:社会や医療に関する情報の収集能力、表現力、礼節力。