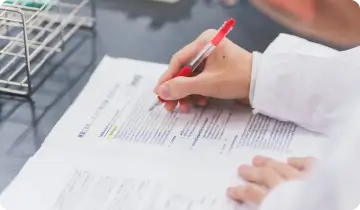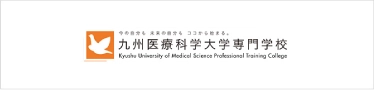教員紹介
准教授
内田 太郎(ウチダ タロウ)
Uchida Taro
Profile
- 所属
- 薬学科
- 主な担当科目
- ・分析化学III
・物理薬剤学
・データサイエンスI・II
- 研究分野
- ・表面振動分光
・電気化学
・電極触媒
・物理化学
・計算化学
・ケモインフォマティクス
・情報科学
- 研究テーマ
- ・どのようにして物質の機能性や反応性が起こるかを分子レベルで明らかにする
私たちの身の回りはさまざまな物質に囲まれています。これらの物質はさまざまな機能性や反応性を持ちます。物質の機能性や反応性はどのようにして起こるのでしょう?これらは物質の表面を構成する分子・原子が、機能性や反応性を示す相手となる物質とどのように相互作用をするかにより決まります。これがはっきりわかれば、新たな機能性や、より反応性の高い物質を作ることがたやすいのですが、わかっていない場合の方がほとんどです。この原因は、「表面」の分子・原子が「表面ではない」分子・原子に比べ圧倒的に数が少ないため、これまでの測定法では「表面」の分子・原子を測ることが難しかったためです。そこで、表面増強赤外分光という、「表面」の分子を高感度に測定できる先端の測定法やコンピュータシミュレーションなどを組み合わせ、物質の機能性や反応性が起こる理由を明らかにしています。
・コンピュータを使って新薬(の候補)をさがす・つくる
薬学の世界では薬と体内のタンパク質は「鍵と鍵穴」と言われ、病気の原因となるタンパク質につよく結合することで働きを制御できる物質が薬となります。薬の探索はこれまで対象のタンパク質に物質を一種類ずつふりかけ、結合するかどうかを実験的に確認するため、時間もお金もかかりました。コンピュータ技術が進歩し、膨大な量の物質からタンパク質に結合するものを効率よくさがしたり、タンパク質により強く結合するようデザインしたりすることができるようになりました。そこで、コンピュタを使い新薬をさがしたり、さらに効率よく探したりデザインしたりする方法の開発を行なったりしています。
・物理系薬学の教材をつくる
薬剤師になるには、大学でさまざまな分野の事柄を学びますが、その中で物理系薬学(ざっくりいうと、薬学で用いる化学の内容を物理の頭で考える分野です)といわれる分野の中身は薬学で学ぶ内容の基礎にも関わらず、とてもとっつきにくいものです。そこで、少しでも親しみを持ってもらい、理解を深めてもらえるように教材の開発を試みています。
- 得意内容
- ・反応を分子レベルで追いかける
・コンピュータを用いて新薬をさがす