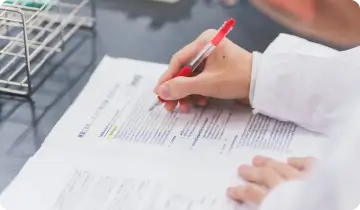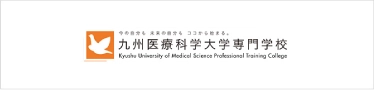救急救命士の役割とは?
病院に搬送されるまでの間または入院するまでの間に救急救命処置を行う
救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受け、医師の指示のもとで「救急救命処置」を行う専門職です。傷病者が病院に搬送されるまで、あるいは到着後に入院するまでの間、症状の悪化を防ぎ、生命を守るための初期対応を担います。
かつて救急救命士は「医師」ではないことから、救急搬送中の医療行為は法律で禁止されていました。しかし、心肺停止患者の救命率・社会復帰率の低さや、目の前で苦しむ患者に適切な処置を施せない救急隊員の苦悩などが社会問題となり、1991年4月に「救急救命士法」が成立。これにより、一定の条件下で一部の医療行為が認められるようになりました。
その後も法改正が重ねられ、救急救命士が行える医療行為の範囲は徐々に拡大。現在の救急医療において、救急救命士は重要な役割を果たす存在となっています。
救急救命士ができること
救急救命士は、医師の指示のもと、以下のような医療行為を実施することが認められています。
-
気道管理
- 口腔・鼻腔を通じた気道確保(バッグバルブマスクの使用)
- 気管挿管(条件付きで実施可能)
-
循環管理
- 静脈路確保(点滴ルートの確立)
- 乳酸リンゲル液などの輸液投与
-
薬剤投与(医師の指示のもと実施)
- アドレナリン(エピネフリン)の投与(心肺停止時)
- ブドウ糖溶液の投与(低血糖発作時)
- 生理食塩水などの補液投与
-
電気的処置
- 自動体外式除細動器(AED)の使用
- マニュアル式除細動器を用いた電気ショック(条件付きで実施可能)
これらの処置を適切に行うことで、救急救命士は病院到着前の傷病者の命をつなぎ、救命率向上に貢献しています。
救急救命士ができないこと
救急救命士は、医療の最前線で活躍する重要な職種ですが、法律により行える医療行為には制限があります。医師ではないため、独自の判断で診断を下したり、高度な医療処置を施したりすることは認められていません。以下に、救急救命士が対応できない主な医療行為を紹介します。
-
診断行為
- 病名の確定や傷病の重症度を判断する行為
- 画像診断(X線・CT・MRIの撮影・読影)
-
外科的処置
- 手術や縫合(傷口の縫合や大きな止血処置)
- 骨折や脱臼の整復(骨を元の位置に戻す処置)
-
特定の医療機器の使用
- 人工呼吸器の装着・管理
- 血液透析や心肺補助装置の操作
-
高度な薬剤投与
- 麻酔薬や鎮痛薬の投与
- 抗生物質やステロイドの投与
救急救命士は、あくまで「病院前救護」において医師の指示のもとに活動する役割を担っており、病院到着後の専門的な診療や治療は医師に引き継がれます。
救急救命士の現状と課題
救急救命士は、救急医療の最前線で活躍し、多くの命を救う重要な役割を担っています。近年、救急件数の増加や高齢化の進行により、救急医療の需要は年々高まっていますが、それに伴いさまざまな課題も浮き彫りになっています。
現状として、救急救命士の役割は拡大しつつあり、法改正により対応できる医療行為の範囲が広がっています。しかし、医療の高度化や救急搬送件数の増加により、救急救命士の負担も大きくなっているのが実情です。
主な課題として、以下のような点が挙げられます。
-
救急搬送の増加と負担の増大
- 高齢化に伴い、軽症患者の救急要請が増加し、救急隊の負担が増えている。
- 病院の受け入れ先が見つからず、救急車が長時間待機する「たらい回し」問題。
-
業務範囲の限界
- 診断行為ができないため、適切な処置を行うために医師の指示を仰ぐ必要がある。
- 救急医療の現場で必要とされる医療行為の一部が、法律上認められていない。
-
キャリアパスの問題
- 救急救命士の資格取得後のキャリアアップの道が限られている。
- 病院内での救急救命士の活用が進んでおらず、働ける場が救急隊に偏っている。
これらの課題を解決するためには、法改正による業務範囲の拡大や、病院・医療機関との連携強化、さらには救急救命士の教育・研修制度の充実が求められています。今後、救急医療のさらなる発展のために、救急救命士の役割をより柔軟に活かせる仕組みづくりが必要とされています。
救急救命士になるには?
救急救命士になるには、救命救急士の国家試験と消防官採用試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。
この条件を満たすには、次の2つの方法があります。
消防官として働いて国家試験を受ける
消防官として採用されてから救急救命士を目指すには、消防官として勤務しながら5年以上または2000時間以上の救急業務を経験し、さらに養成所で7か月以上の講習を受けることで受験資格が得られます。
養成学校を卒業して消防官に採用される
養成課程のある大学や専門学校で所定の課程を修了し、国家試験に合格したのちに、各自治体の消防官採用試験を受験します。
救急救命士を目指すなら「九州医療科学大学」
救急救命士を目指すなら、現場での活躍を見据えた実践的な学びを深められる九州医療科学大学がおすすめです。オープンキャンパスへのお申込みや資料請求をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。